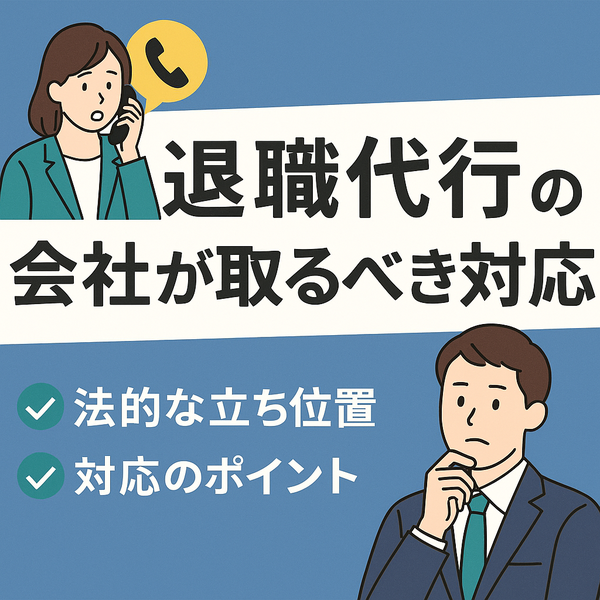
「突然、退職代行から電話が…📞」
そんな相談が、ここ沖縄でも増えてきています。
退職の意思を、労働者本人に代わって会社へ伝える「退職代行サービス」。
年度末や新年度、人手不足の業界では特に利用が増えており、企業側も油断できません。
今回は、
✅ 退職代行の法的な立ち位置
✅ 会社がとるべき対応のポイント
をわかりやすく解説します。
◆ 退職代行って違法?合法?
退職代行業者が「本人に代わって退職の意思を伝える」行為は、法的には「使者」または「代理人」として整理されます。
-
使者:本人が決めた内容をそのまま相手に伝えるだけの役割
-
代理人:本人に代わって交渉や意思決定を行う存在
この違いが、対応の可否を分ける重要なポイントです。
▶ 使者としての行為(意思を伝えるだけ)であれば合法
▶ 交渉(退職日の調整・未払い賃金請求など)に踏み込むと非弁行為となる可能性があり違法となることも
つまり、弁護士資格のない業者が条件交渉を行うことは、原則として法律違反とされるおそれが高いのです。
◆ 退職代行から連絡が来たら、どうするべき?
まず大前提として、退職の意思表示は民法627条により「2週間前に申し出があれば退職可能」とされています。
しかし、退職代行業者から突然連絡があったとしても、その場で「退職扱い」にしてしまうのは危険です。
🔸 実務上の注意点
1. 本人の意思かどうか、必ず確認する
退職代行業者から連絡があっても、本人の署名入りの書面(退職届など)を必ず求めましょう。
本人名義でない場合、退職の効力が認められない可能性があります。
2. 電話対応だけで処理しない
電話連絡だけでは記録が残らず、後日のトラブルにつながりかねません。
退職届は書面での提出を原則とするルールを社内で徹底しましょう。
3. 交渉は弁護士以外には応じない
退職日や条件に関する交渉を持ちかけられた場合、相手が弁護士資格を有しているかを必ず確認しましょう。
弁護士でない業者が交渉することは「非弁行為」に該当する可能性があり、対応する必要はありません。
💼 退職代行サービスの実態と、対応可能な範囲
退職代行と一口に言っても、「できること」と「できないこと」がはっきりと分かれています。
以下は、弁護士でない退職代行業者と弁護士の対応可能な範囲を比較したものです。
| 対応内容 | 弁護士でない退職代行業者 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 退職の意思を伝える | ◯(使者として) | ◯ |
| 退職日の調整、有給消化交渉 | × | ◯ |
| 未払い賃金・残業代の請求 | × | ◯ |
| 損害賠償の対応 | × | ◯ |
💡それぞれの対応内容の詳細
● 退職の意思を伝える
📌 弁護士でない業者でも「退職の意思を伝えるだけ」なら合法です。
企業側としては、退職代行業者から連絡が来た場合でも、本人の意思表示かどうかを確認することが重要です。
書面(退職届等)の提出を求め、署名が本人のものかを確認する対応が基本です。
● 退職日の調整・有給休暇の消化交渉
📌 このような「交渉行為」は、弁護士にしか認められていません。
弁護士でない業者から「有給を消化させたい」「退職日を調整したい」といった交渉の申し出があっても、企業としては応じる必要はありません。
むしろ、応じてしまうことで法的なグレーゾーンに巻き込まれるリスクすらあります。
● 未払い賃金・残業代の請求
📌 弁護士でない退職代行業者が「未払い賃金を支払ってください」といった主張をしてきた場合も、企業としては取り合わないことが原則です。
このような交渉が必要な場合は、弁護士が対応してくるかどうかを確認し、正式な法的主張であれば書面で受け取るようにしましょう。
● 損害賠償に関する対応
📌 「引き継ぎがされなかった」などの理由で、企業側が損害賠償を検討する場合でも、退職代行業者とのやり取りでは法的な交渉ができません。
逆に、労働者側から損害賠償に関する主張があった場合でも、それを伝えてきたのが弁護士でなければ、交渉には一切応じる必要はありません。
🏢企業としての対応ポイント
退職代行から会社に連絡があった場合、まずは以下の点を確認することが大切です。
-
本人の意思確認
-
退職代行業者からの連絡だけではなく、必ず書面(退職届)で確認を行い、本人の署名があるかチェックしましょう。
-
-
電話での連絡は記録が残らないため注意
-
電話連絡のみの場合は、後日トラブルになりやすいため、書面での受付が基本です。
-
-
交渉が必要な場合は弁護士の確認を
-
万が一、退職日の調整や有給消化、未払い賃金などの交渉を求められた場合、弁護士が対応できるかどうかを確認し、弁護士の関与を検討しましょう。
-
💬まとめ
退職代行サービスには、伝達のみ対応可能な「使者」としての役割と、交渉や法的請求が可能な弁護士の役割とでは大きな違いがあります。企業としては、退職の意思表示がどのように伝えられているのか、そして交渉が必要な場合にどの専門家が介入しているかをしっかりと見極め、正確な確認と適切な対応を心がけることが重要です。
もし、退職代行に関する具体的なトラブルや、対応方法についてお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
つばさ社会保険労務士事務所が、沖縄企業様の安心できる労務管理をしっかりサポートいたします!
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由





