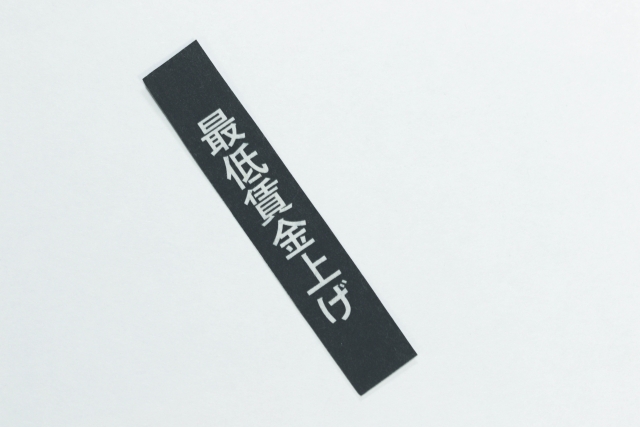
※8月5日最新コラムをアップしました!併せてご確認ください!
こんにちは。沖縄の社会保険労務士、玉城です。
今回は、いよいよ現実味を帯びてきた「最低賃金1,000円時代」に向けて、沖縄の企業がどう備えるべきかをわかりやすく解説します。
📈沖縄でも1,000円突破が目前に
沖縄県の最低賃金は、ここ数年で大きく引き上げられてきました。
-
2022年:853円
-
2023年:896円(+43円)
-
2024年:952円(+56円)
このペースが続けば、2025年に1,000円を超える可能性は十分にあります。
全国平均はすでに1,004円に到達しており、沖縄もその流れに追随する形となるのは自然な流れです。
🕒最低賃金の改定は「毎年10月ごろ」が通例
最低賃金は、毎年夏に厚生労働省の中央最低賃金審議会で目安額が示され、その後、各都道府県で最終決定されます。
そして実際の施行は、例年10月1日〜中旬ごろとなるのが通例です。
💼企業にとっての影響は小さくない
最低賃金が上がると、当然ながら時給ベースの労働者の給与コストが上昇します。
特にパート・アルバイト比率が高い業種では、経営に直接響く要因となりえます。
-
既存スタッフとの賃金逆転現象のリスク
-
求人時給の上昇による採用競争の激化
-
価格転嫁の判断を迫られるケースも
一方で、賃上げを前向きに捉えることも重要です。
人材確保・定着率向上・企業イメージアップなど、賃上げによるプラスの効果も見逃せません。
🛠最賃1,000円時代に向けて今できる備え
① 業務の見直し・人材配置の最適化
-
単なる人手不足解消ではなく、「業務内容」と「人材のスキル」の再設計
-
非効率業務の洗い出しと委託・内製の整理
② 生産性向上・DXの活用
-
勤怠・給与・シフトのクラウド化による管理コスト削減
-
業務の標準化・マニュアル化を進め、誰でも一定品質で回る職場へ
③ 賃金制度の整備
-
最低賃金上昇に合わせ、全体の賃金バランスを見直す
-
処遇の明確化、評価制度との連動などで納得感を持たせる
💡賃上げに取り組む企業を支援する制度【2025年版】
賃上げは、経営資源に余裕がない中小企業にとって容易なものではありません。
そこで国は、「前向きな取り組み」をサポートするため、さまざまな助成・減税・融資制度を用意しています。
✅1. 業務改善助成金
-
概要:最低賃金を30円~90円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に助成
-
助成上限額:最大600万円
-
対象経費:就業管理ソフト、レジ導入、作業効率改善機器など
✅2. キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
-
概要:パート・契約社員などの非正規労働者の賃金規定を増額改定し、実際に運用した場合に助成
-
助成額:1人あたり最大7万円(賃上げ率による)
✅3. 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・設備導入等)
-
概要:離職率の改善や処遇改善を目的に、評価制度・健康づくり制度・作業軽減機器導入などを行った場合に助成
-
助成額:最大287.5万円(賃上げを行った場合)
🧾税制・融資による支援も活用できます
✅4. 賃上げ促進税制
-
概要:給与支給額が前年度比1.5%以上増加した場合、法人税額から最大30%控除
✍まとめ|制度を活用し、現実的に備える時代へ
最低賃金1,000円の到来は、コスト増だけでなく、「企業としての在り方」が問われる時代へのシフトです。
制度を知り、使いこなすことで、現実的かつ前向きな対応が可能になります。
📣つばさ社会保険労務士事務所では、制度の選定から活用サポート、職場改善のアドバイスまでトータルでご相談をお受けしています。
まずは小さな一歩から、一緒に準備を進めませんか?
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由





