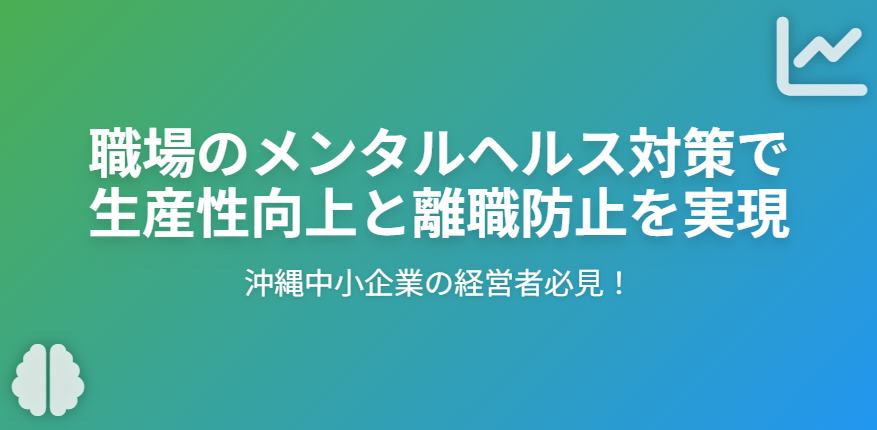
こんにちは。つばさ社会保険労務士事務所の玉城翼です。
沖縄県内の中小企業経営者の皆様から「従業員のメンタルヘルス不調にどう対応すればいいのか」というご相談が増えています。第14次労働災害防止計画では、2028年3月までにメンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上にするという目標が掲げられました。
今回は、厚生労働省の指針をもとに、沖縄の中小企業でも無理なく始められるメンタルヘルス対策について解説します。
なぜ今、メンタルヘルス対策が必要なのか
令和4年の調査では、仕事や職業生活で強い不安やストレスを感じている労働者の割合は82.2%に達しています。また、精神障害による労災認定件数は年々増加傾向にあり、職場のいじめ・嫌がらせに関する相談も全体の27.9%を占めるまでになりました。
沖縄県内の中小企業においても、人材確保が困難な中で従業員の心の健康を守ることは、企業存続に直結する重要課題です。メンタルヘルス不調による休職や離職は、残された従業員への負担増加、採用・育成コストの発生、さらには企業イメージの低下にもつながります。
中小企業が押さえるべき「4つのケア」
メンタルヘルス対策の基本は「4つのケア」の継続的な実施です。
1. セルフケア(従業員自身による)
従業員がストレスやメンタルヘルスについて理解し、自らのストレスに気づき対処できるよう教育研修や情報提供を行います。ストレスチェックの活用も効果的です。
2. ラインによるケア(管理監督者による)
日常的に部下と接する管理監督者が「いつもと違う」部下の変化に気づき、話を聴き、必要に応じて産業医や専門家につなぐ役割を果たします。
3. 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
産業医、衛生管理者、保健師などが専門的立場から、従業員や管理監督者を支援します。
4. 事業場外資源によるケア
産業保健総合支援センターや医療機関など外部の専門家を活用します。小規模事業場では特に重要です。
沖縄の中小企業でも実践できる具体的ステップ
ステップ1:経営者の方針表明
まず、経営者自身が「従業員の心の健康を守る」という明確なメッセージを発信することが重要です。朝礼や社内報、掲示板などで繰り返し伝えましょう。
ステップ2:相談しやすい環境づくり
従業員が気軽に相談できる窓口を設置します。社内に産業医や保健師がいない場合は、沖縄産業保健総合支援センター(098-859-6175)の無料相談を活用できます。
ステップ3:管理監督者への研修実施
管理監督者が部下の変化に気づき、適切に対応できるよう、以下の内容を含む研修を実施します。
| 研修テーマ | 具体的内容 |
|---|---|
| 部下の変化への気づき | 遅刻・欠勤の増加、業務効率の低下、表情の変化など、メンタルヘルス不調のサインを学ぶ |
| 話の聴き方 | 積極的傾聴法を用いた相談対応の基本スキルを習得する |
| 職場環境の改善 | 業務量の調整、コミュニケーションの活性化など具体的な改善策を学ぶ |
| 連携の方法 | 産業医や人事部門、外部専門家への相談・連携の手順を理解する |
ステップ4:ストレスチェックの実施
従業員数50人以上の事業場では年1回の実施が義務付けられていますが、50人未満でも実施を推奨します。個人の気づきを促すとともに、集団分析により職場全体のストレス状況を把握し、職場環境改善につなげることができます。
ステップ5:職場環境の改善
ストレスチェックの結果や日常の観察から、職場環境の問題点を把握し改善します。沖縄の企業文化に配慮しながら、以下のような取組みが効果的です。
| 改善の視点 | 具体的な取組み例 |
|---|---|
| 業務量・時間 | 長時間労働の削減、業務の見える化と平準化、休暇取得の促進 |
| コミュニケーション | 定期的な1on1面談、気軽な相談の場づくり、感謝や承認の言葉がけ |
| 職場の人間関係 | ハラスメント防止研修、チームビルディング、風通しの良い職場文化の醸成 |
| 物理的環境 | 休憩スペースの確保、照明・温度の調整、デスク配置の工夫 |
職場復帰支援も重要なポイント
メンタルヘルス不調で休業した従業員が円滑に職場復帰できるよう、あらかじめ職場復帰支援プログラムを策定しておくことが望ましいです。復帰直後はいきなり以前と同じ業務量を期待せず、段階的に業務を増やしていく配慮が必要です。
管理監督者は「職場では自分をどう思われているか」「また悪くならないか」と不安を抱える復職者の気持ちを受け止め、温かく迎え入れる姿勢が大切です。
個人情報保護への配慮を忘れずに
メンタルヘルス対策を進める上で最も注意すべきは、健康情報を含む個人情報の保護です。相談内容や健康情報は、本人の同意なく第三者に漏らしてはいけません。
ストレスチェックの結果は、本人の同意がない限り事業者に提供できません。また、メンタルヘルス不調を理由とした解雇、退職勧奨、不当な配置転換などの不利益取扱いは絶対に行ってはなりません。
小規模事業場こそ外部資源の活用を
従業員数50人未満の小規模事業場では、社内に産業医や保健師を確保することが難しい場合が多いでしょう。そのような場合こそ、外部資源を積極的に活用することが効果的です。
沖縄産業保健総合支援センター(098-859-6175)では、ストレスチェックの導入支援、メンタルヘルス不調の予防から職場復帰支援まで、無料で総合的な相談に応じています。また、当事務所のような社会保険労務士も、就業規則の整備やメンタルヘルス対策の体制づくりをサポートできます。
まとめ:予防的アプローチが企業の未来を守る
メンタルヘルス対策は、問題が起きてから対応するのではなく、予防的に取り組むことが重要です。従業員が心身ともに健康で働ける職場環境を整えることは、生産性の向上、離職率の低下、企業イメージの向上につながります。
沖縄の中小企業の皆様が、従業員の心の健康を守りながら、持続的に成長していけるよう、当事務所は実務に根ざした支援を提供してまいります。メンタルヘルス対策に関するご相談は、お気軽につばさ社会保険労務士事務所までお問い合わせください。
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由




