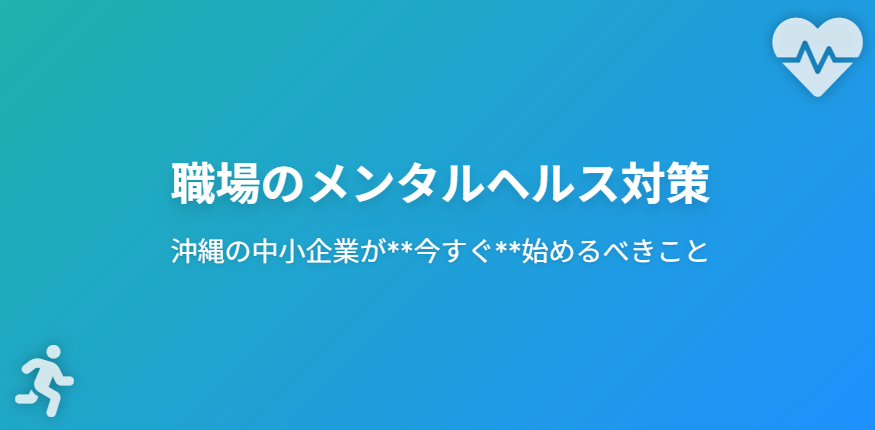
「最近、従業員の元気がない気がする」「急な休職者が出て現場が回らなくなった」――こんなお悩みを抱えていませんか?
職場のメンタルヘルス対策は、大企業だけの課題ではありません。沖縄県内の中小企業においても、従業員の心の健康を守ることは、事業の持続的な成長に直結する重要なテーマです。
この記事では、従業員数50名以下の企業でも無理なく取り組める具体的な対策と、専門家への相談タイミングについて解説します。読み終えた後には、明日から実践できる第一歩が見えてくるはずです。
なぜ今、職場のメンタルヘルス対策が必要なのか
近年、働く方のメンタルヘルス不調は増加傾向にあります。厚生労働省の調査によれば、精神障害による労災認定件数は過去最高水準で推移しており、業種や企業規模を問わず対策が求められています。
従業員50名未満でも取り組むべき理由
ストレスチェック制度の義務化は従業員50名以上の事業場が対象ですが、義務がないからといって対策不要というわけではありません。むしろ、小規模事業場では従業員一人ひとりの役割が大きく、一人の休職が事業運営に与える影響は深刻です。
沖縄県内の企業では、観光業や建設業など繁閑期のある業種において、繁忙期の長時間労働によるストレス蓄積が課題となるケースが多く見られます。また、家族的な雰囲気の職場だからこそ、「相談しにくい」「迷惑をかけたくない」という心理的なハードルが生まれることもあります。
予防的な視点で職場環境を整えることは、従業員の離職防止や採用力の向上にもつながり、結果として企業の競争力を高めることになります。
中小企業でも無理なく始められる3つのステップ
メンタルヘルス対策と聞くと、「専門知識が必要そう」「費用がかかりそう」と感じるかもしれません。しかし、まずは小さな一歩から始めることが大切です。
ステップ1:職場環境の現状把握
最初に取り組むべきは、現在の職場環境を客観的に見直すことです。具体的には以下の点を確認してみましょう。
- 長時間労働や休日出勤が常態化していないか
- 従業員同士のコミュニケーションは円滑か
- 業務の役割分担が特定の人に偏っていないか
- 休憩時間や年次有給休暇が適切に取得されているか
当事務所がこれまで対応してきた相談事例では、経営者自身が「問題ない」と考えていた職場でも、従業員へのヒアリングを通じて潜在的な課題が明らかになるケースが少なくありません。
ステップ2:相談窓口の設置
従業員が「困ったときに相談できる場所」を明確にすることは、予防的対策の要です。社内に産業医や衛生管理者がいない場合でも、以下のような方法があります。
- 外部の相談機関(産業保健総合支援センターなど)の情報を掲示する
- 社会保険労務士など外部専門家との連携体制を整える
- 定期的な個別面談の機会を設ける
沖縄県内には、地域産業保健センター(地さんぽ)が設置されており、従業員50名未満の事業場は無料で産業保健サービスを利用できます。このような公的支援制度を積極的に活用することで、費用負担を抑えながら専門的なサポートを受けることが可能です。
ステップ3:継続的なケア体制づくり
一度対策を講じただけでは十分とは言えません。職場環境は日々変化するため、継続的な取り組みが必要です。
| 企業規模 | 必須対応項目 | 推奨対応項目 |
|---|---|---|
| 従業員10名未満 |
・労働時間の適正管理 ・相談窓口情報の周知 |
・年1回の職場環境確認 ・外部専門家との連携 |
| 従業員10~49名 |
・労働時間の適正管理 ・相談窓口情報の周知 ・定期的な面談機会の設定 |
・ストレスチェックの任意実施 ・メンタルヘルス研修の実施 |
| 従業員50名以上 |
・上記全て ・ストレスチェックの実施(義務) ・衛生委員会の設置 |
・復職支援プログラムの整備 ・産業医との連携強化 |
当事務所が支援した沖縄県内の製造業の事例では、従業員約30名の企業において、月1回の短時間面談制度と外部相談窓口の設置を導入しました。その結果、従業員から「以前より相談しやすくなった」という声が聞かれるようになり、メンタルヘルス不調の兆候を早期に発見できる体制が整いました。休職が必要なケースでも、早期対応により約3か月での職場復帰を実現しています。
📄 外部サイト: 「メンタルヘルス対策成功事例集(外部サイト)」
こころの耳(厚生労働省):職場のメンタルヘルス対策の取組事例
専門家に相談するタイミングと支援制度
自社だけでの対応に限界を感じたとき、あるいは予防的な体制を本格的に構築したいとき、専門家の力を借りることは有効な選択肢です。
こんな兆候があれば早めの相談を
以下のような状況が見られる場合は、早めに社会保険労務士や産業保健の専門家へご相談ください。
- 従業員の遅刻や欠勤が増えている
- 業務のミスやトラブルが目立つようになった
- 職場の人間関係に関する相談が増えている
- 長時間労働が恒常化しており改善の糸口が見えない
- 休職者が発生したが対応方法がわからない
メンタルヘルス不調は、早期発見・早期対応が何より重要です。「様子を見よう」と先延ばしにすることで、症状が悪化し、休職期間が長期化したり、最悪の場合には離職につながることもあります。
沖縄県内では、産業保健総合支援センターや労働基準監督署でも相談を受け付けています。また、社会保険労務士は労務管理の専門家として、法令遵守の観点から職場環境改善のサポートを行います。当事務所では、初回相談を無料で承っており、現状をお伺いした上で、御社に最適な対策をご提案いたします。
メンタルヘルス対策は、単なる法令対応ではなく、従業員一人ひとりが安心して働ける環境をつくるための投資です。沖縄の企業文化に合った、無理のない形で取り組みを進めていくことが、持続可能な組織づくりの第一歩となります。
まとめ
今日から始められる3つのステップ:
- 現在の職場環境を客観的に見直し、課題を洗い出す
- 従業員が相談できる窓口情報を整理し、周知する
- 外部の支援制度(地さんぽ等)を活用し、専門家との連携体制を整える
メンタルヘルス対策は、特別なことではありません。日々の業務の中で「いつもと違う」様子に気づき、適切に対応できる体制を整えることから始まります。
📞 無料相談のご予約
職場のメンタルヘルス対策でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由




