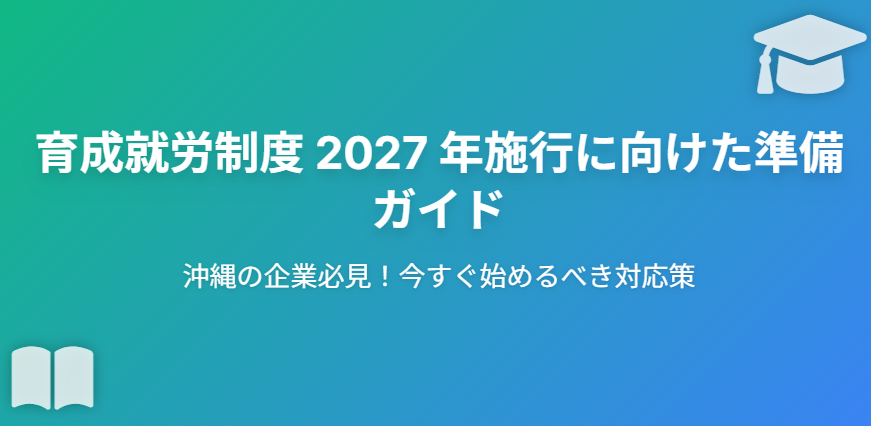
「外国人材の受入れを検討しているが、制度が変わると聞いて不安」「技能実習生を雇用しているけれど、今後どうなるのか」—そんなお悩みはありませんか。令和7年10月1日、育成就労制度が令和9年4月1日から施行されることが正式に決定しました。この記事では、沖縄県内の中小企業の皆様に向けて、新制度の概要と今から準備すべきポイントを社会保険労務士の視点から解説します。施行まで約1年半、余裕を持った準備が企業の競争力を左右します。
育成就労制度とは?技能実習制度からの大きな転換
育成就労制度は、これまでの技能実習制度を抜本的に見直し、令和9年4月1日から施行される新しい外国人材の受入れ制度です。最大の特徴は、制度の目的が「国際貢献のための技能移転」から「日本の人手不足分野における人材の育成・確保」へと明確に転換された点にあります。
技能実習との決定的な違い
従来の技能実習制度では、原則として転籍(職場の変更)が認められませんでした。しかし育成就労制度では、一定の要件を満たせば本人の意向による転籍が可能になります。これは労働者としての権利保護を重視した改正であり、企業側には「選ばれる職場づくり」がこれまで以上に求められることを意味します。
また、育成就労制度では3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を習得させることが明確な目標として設定されています。修了後は特定技能1号へスムーズに移行でき、最長8年間(育成就労3年+特定技能1号5年)の雇用継続が可能です。さらに特定技能2号へ移行すれば、在留期間の制限なく長期雇用の道が開けます。
沖縄で想定される受入れ分野
育成就労制度の受入れ対象分野は、特定技能制度と原則一致します。沖縄県内の企業で特に関連が深いと考えられる分野は、宿泊業、建設などです。観光産業が盛んな沖縄では、ホテルやレストランでの人手不足が深刻化しており、今後これらの分野での活用が見込まれます。当事務所でも、沖縄中部地域の製造業の経営者様から「今後の外国人材受入れについてどう準備すればよいか」というご相談が増えています。
沖縄の企業が今から準備すべき3つのポイント
令和9年4月の施行に向けて、企業が今から取り組むべき準備は大きく3つあります。いずれも時間を要する手続きですので、早期の着手が重要です。
1. 育成就労計画の認定準備
育成就労制度では、外国人材ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構による認定を受ける必要があります。この計画には、育成就労の期間(3年以内)、育成目標(業務内容、習得させる技能、日本語能力の目標など)、具体的な育成方法などを記載します。
計画の認定基準はまだ詳細が公表されていませんが、技能実習制度よりも厳格化されることが想定されます。特に、「3年間で特定技能1号水準の技能を習得させる」という明確な目標達成に向けた実効性のある育成計画が求められるでしょう。
準備のポイントとしては、まず自社の業務内容を棚卸しし、どの業務でどのような技能を段階的に習得させるかを整理することです。OJT(職場内訓練)だけでなく、Off-JT(座学研修や外部研修)の計画も必要になる可能性があります。
2. 監理支援機関との連携体制の構築
育成就労制度では、監理支援機関が重要な役割を担います。監理支援機関は、企業と外国人材の雇用関係成立のあっせんや、適正な育成就労が実施されているかの監査などを行います。
技能実習制度の監理団体も、新たに監理支援機関としての許可を受ける必要があります。許可基準は厳格化される見込みですので、現在お付き合いのある監理団体が監理支援機関の許可を取得する予定かどうか、早めに確認しておくことをお勧めします。
なお、一定規模以上の企業であれば、監理支援機関を通さず直接外国人材を受け入れる「単独型育成就労」も可能です。ただし、募集から計画作成、受入れ後の支援まで全て自社で対応する必要があるため、中小企業では監理支援機関との連携が現実的でしょう。
3. 就業環境の整備と労務管理体制の見直し
育成就労制度では、本人意向による転籍が認められるため、外国人材に「この会社で働き続けたい」と思ってもらえる職場環境づくりが不可欠です。
具体的には、適正な賃金水準の確保、労働時間管理の徹底、安全衛生対策の強化、相談しやすい体制づくりなどが求められます。特に沖縄では、台風や高温多湿といった気候条件に不慣れな外国人材への配慮も重要です。
また、日本語教育の支援体制も整備しておきましょう。育成就労制度では、入国時に日本語能力試験N5相当以上(または相当する日本語講習の受講)が求められますが、3年間の育成期間を通じてさらに日本語能力を向上させる取組が評価されます。
| 確認項目 | 準備内容 | 準備期限の目安 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 育成就労計画の素案作成 | 業務内容の棚卸し、育成目標の設定、研修計画の策定 | 施行6か月前まで | 人事・現場責任者 |
| 監理支援機関の選定 | 既存監理団体の許可取得状況確認、新規機関の比較検討 | 施行9か月前まで | 人事・総務 |
| 就業環境の整備 | 賃金水準の見直し、住居の確保、相談窓口の設置 | 施行3か月前まで | 人事・総務 |
| 就業規則の見直し | 外国人雇用に対応した規定の追加・修正 | 施行6か月前まで | 人事・総務 |
| 二国間取決め(MOC)の確認 | 受入れ予定国とのMOC締結状況の確認 | 随時 | 人事 |
施行までのスケジュールと具体的なアクションまとめ
育成就労制度は、日本の人手不足分野における持続的な人材確保を目指した新しい仕組みです。技能実習制度からの転換により、外国人材の権利保護が強化され、企業には「選ばれる職場」としての魅力づくりが求められます。
沖縄県内の中小企業にとって、観光業や製造業での人手不足は喫緊の課題です。育成就労制度を適切に活用することで、長期的に企業を支える人材を確保できる可能性が広がります。
今日から始められる3つのステップ:
- 自社の業務内容を棚卸しし、どの分野で外国人材を活用できるか検討する
- 現在お付き合いのある監理団体に、監理支援機関の許可取得予定を確認する
- 外国人材の受入れを前提とした就業環境の改善点をリストアップする
施行まで約1年半という準備期間を有効に活用し、新制度への円滑な移行を実現しましょう。つばさ社会保険労務士事務所では、育成就労制度への対応を含め、沖縄の中小企業の皆様の労務管理をトータルでサポートいたします。
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由




