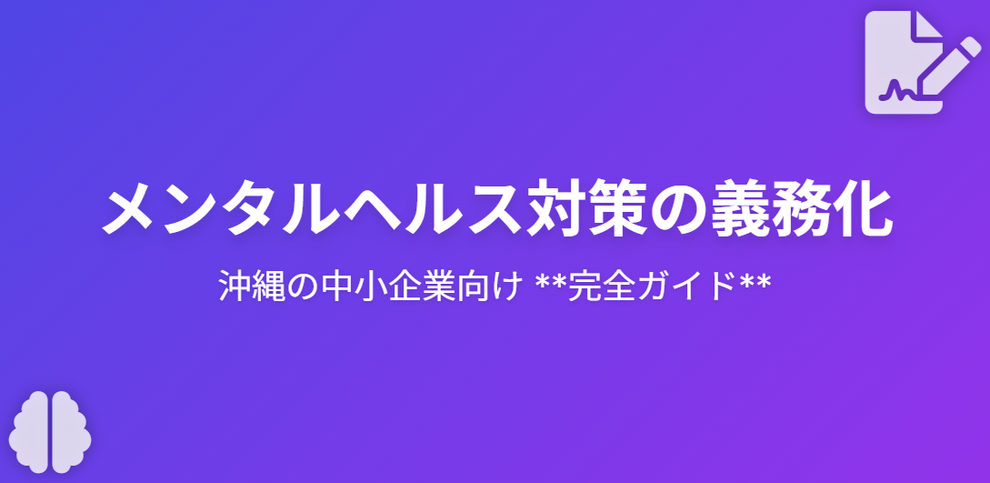
こんなお悩みはありませんか?
「従業員が最近元気がない」「ストレスチェックって50人未満の会社も必要なの?」「メンタルヘルス対策、何から始めればいいかわからない」
沖縄県内の中小企業経営者の皆さま、このようなお悩みを抱えていませんか?
この記事では、令和10年5月頃までに義務化されるストレスチェック制度の準備方法と、沖縄の企業文化に適した実践的なメンタルヘルス対策をわかりやすく解説します。読み終えた後には、明日から取り組める具体的なアクションが明確になります。
なぜ今、沖縄の中小企業でメンタルヘルス対策が必要なのか
精神障害の労災認定が過去最多を更新
令和6年度の精神障害の労災認定件数は1,055件と過去最多を記録しました。その原因の第1位は「パワーハラスメント」(224件)、続いて「仕事内容・仕事量の大きな変化」(119件)となっています。
沖縄県内の中小企業でも、観光業の繁閑期における業務量の変動や、人手不足による従業員への負担増加が深刻化しています。メンタルヘルス不調により1か月以上休業または退職した労働者がいる事業場の割合は、全国的に上昇傾向にあり、もはや「他人事」では済まされない状況です。
国が掲げる明確な目標値
第14次労働災害防止計画では、令和9年までに以下の目標が設定されています。
- メンタルヘルス対策に取り組む事業場:80%以上
- 50人未満の事業場のストレスチェック実施率:50%以上
しかし現状では、30〜49人の事業場で71.8%、10〜29人の事業場では56.6%にとどまっており、小規模事業場での取り組みが急務となっています。
沖縄の企業が直面しやすい課題
沖縄県内の中小企業では、以下のような特有の課題があります。
- 観光業における繁忙期(夏季・年末年始)の長時間労働
- 台風などの自然災害による営業への影響とストレス
- 離島や遠隔地での人材確保の困難さ
- 家族的な職場文化ゆえの相談しにくさ
これらの課題に対し、予防的なメンタルヘルス対策を講じることで、従業員の健康を守りながら、生産性の向上と離職率の低下を実現できます。
ストレスチェック義務化で変わること 50人未満の事業場も対象に
令和10年5月頃までに義務化
労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化されます。
義務化される主な内容:
- ストレスチェックの実施(年1回)
- 高ストレス者への医師による面接指導
- 集団分析による職場環境改善
- 結果の5年間保存
対象となる労働者
ストレスチェックの対象は「常時使用する労働者」です。具体的には、以下の2つの要件を満たす方が対象となります。
- 期間の定めのない労働契約、または1年以上の契約期間がある方(更新により1年以上の雇用が見込まれる方を含む)
- 週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上である方
なお、週の労働時間が2分の1以上である短時間労働者にも、実施することが望ましいとされています。
| 事業場規模 | ストレスチェック | ハラスメント対策 | 相談窓口設置 |
|---|---|---|---|
| 50人以上 | 義務(現行) | 義務 | 義務 |
| 50人未満 | 義務(R10.5までに〜) | 義務 | 推奨 |
| すべての事業場 | 集団分析による職場環境改善(努力義務) | ||
| すべての事業場 | 心の健康づくり計画の策定(推奨) | ||
|
📄 事例資料ダウンロード: 事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集
企業がどのように対策を進めたかを詳しく解説 |
実施にかかる費用の目安
外部機関を活用する場合、ストレスチェック本体の費用は1人あたり500〜1,000円程度、集団分析は1事業場あたり2,000〜5,000円程度が相場です。
50人未満の事業場の負担を考慮し、厚生労働省は産業保健活動総合支援事業(地域産業保健センター)による無料支援も提供しています。
明日から始める|中小企業のための実践的メンタルヘルス対策
ステップ1:体制整備から始める
メンタルヘルス対策は、いきなり完璧を目指す必要はありません。まずは以下の基本体制を整えましょう。
今すぐできる3つのこと:
-
衛生委員会の設置または既存の会議での議題化
従業員代表を含めた話し合いの場を月1回設けます。50人未満の事業場では、全体ミーティングでの議題化でも構いません。 -
相談窓口の明確化
「メンタル面で困ったことがあれば○○さん(総務担当者など)に相談してください」と全従業員に周知します。外部の相談窓口(こころの耳相談ダイヤル:0120-565-455)も案内しましょう。 -
心の健康づくり計画の策定
A4用紙1枚程度で構いません。「当社は従業員の心の健康を大切にします」という方針と、担当者、年間スケジュールを記載します。
ステップ2:ストレスチェックの準備と実施
実施者の選定:
ストレスチェックは、医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、公認心理師が実施できます。
沖縄県内の地域産業保健センターや、健康診断を委託している健診機関に相談することで、外部実施者の紹介を受けられます。
実施の流れ:
- 質問票の配布(57項目の職業性ストレス簡易調査票を推奨)
- 実施者による評価・判定
- 本人への結果通知(事業者には本人の同意なく提供できません)
- 高ストレス者からの申し出に基づく医師面接指導
- 医師の意見を踏まえた就業上の措置
ステップ3:4つのケアで職場環境を改善
厚生労働省の指針では、効果的なメンタルヘルス対策として「4つのケア」を推奨しています。
セルフケア(従業員自身によるケア):
ストレスへの気づきと対処方法を学ぶ機会を提供します。朝礼での簡単なストレッチや、休憩時間の確保など、日常に取り入れやすい取り組みから始めましょう。
ラインによるケア(管理監督者によるケア):
管理職や現場リーダーが、部下の変化に気づき、声をかけられる体制をつくります。「最近どう?」という何気ない一言が、早期発見につながります。
事業場内産業保健スタッフ等によるケア:
産業医や保健師がいない小規模事業場では、地域産業保健センターの保健師による訪問指導(無料)が活用できます。
事業場外資源によるケア:
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、メール相談、電話相談、SNS相談が無料で利用できます。従業員への周知をお勧めします。
実際の成功事例:沖縄県内A社の取り組み
従業員約30名の観光関連企業A社では、繁忙期の長時間労働により、メンタル不調を訴える従業員が出始めました。
同社では以下の対策を実施しました:
- 月1回の全体ミーティングでメンタルヘルスを議題化
- 繁忙期前の健康診断とストレスチェックの実施
- 業務の平準化と、ピーク時の応援体制の構築
その結果、従業員の離職率が減少し、お客様満足度も向上しました。予防的な取り組みが、従業員と会社の双方にメリットをもたらした好例です。
よくある失敗パターンと回避策
失敗例1: ストレスチェックを実施しただけで終わってしまう
→ 回避策: 集団分析の結果をもとに、具体的な職場環境改善策を1つでも実施する
失敗例2: 相談窓口を設置したが誰も利用しない
→ 回避策: 匿名性を確保し、「相談したことが人事評価に影響しない」ことを明確に伝える
失敗例3: 管理職が部下の変化に気づかない
→ 回避策: 年1回でも、管理職向けのラインケア研修を実施する(オンライン研修や「こころの耳」のe-ラーニングも活用可能)
まとめ 今日から始める3つのステップ
メンタルヘルス対策は、従業員の健康を守るだけでなく、生産性向上と人材定着にもつながる重要な経営課題です。
要点の3行まとめ:
- 令和10年5月から、50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化されます
- 相談窓口の設置、4つのケアの実践、ハラスメント対策が予防の鍵です
- 地域産業保健センターや「こころの耳」など、無料で使える支援制度を活用しましょう
今日から始められる3つのステップ:
- 衛生委員会や全体会議でメンタルヘルスを議題にする
- 相談窓口(内部担当者+外部窓口)を明確にして全従業員に周知する
- 心の健康づくり計画(簡易版でOK)を作成する
📞 無料相談のご予約
メンタルヘルス対策の進め方、ストレスチェックの準備、ハラスメント対策など、労務管理でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
つばさ社会保険労務士事務所では、沖縄の中小企業に特化した実務サポートを提供しています。
初回相談は無料です。
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由




