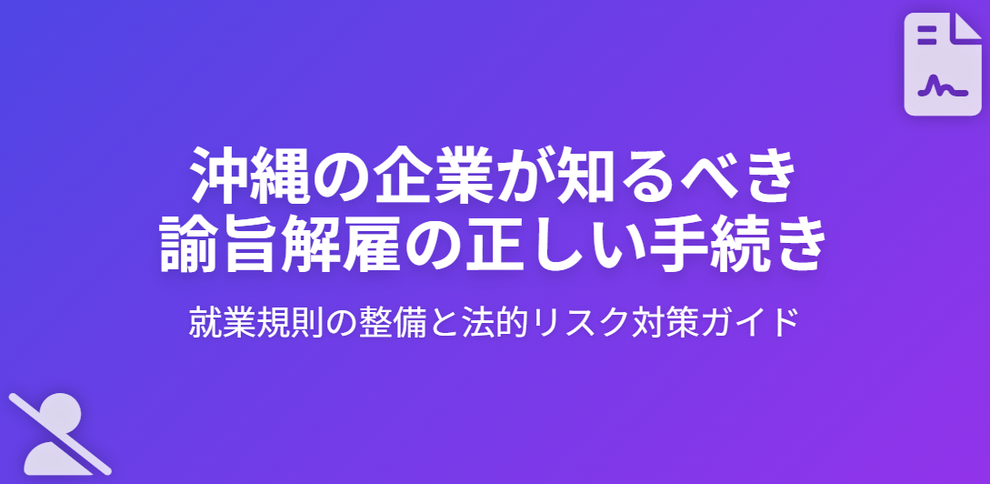
従業員の重大な規律違反に直面したとき、「解雇したいが、トラブルは避けたい」とお悩みではありませんか?諭旨解雇(ゆしかいこ)は、懲戒解雇よりも穏便に雇用関係を終了させる選択肢として、多くの企業で活用されています。しかし、手続きを誤れば不当解雇として訴訟リスクを抱えることになります。本記事では、沖縄の中小企業が諭旨解雇を適切に実施するための要件と手続き、そして就業規則の整備ポイントを具体的に解説します。
諭旨解雇(諭旨退職)とは?
諭旨解雇とは、企業が従業員に対して退職を勧告し、一定期間内に退職届の提出を求める懲戒処分の一種です。沖縄県内の企業においても、特に観光業や製造業などで繁忙期と閑散期の差が大きい業界では、雇用調整の一環として検討されることがあります。
この処分は懲戒解雇に次ぐ重い処分でありながら、従業員に退職届を提出させることで、形式上は「自己都合退職」として処理できるという特徴があります。企業にとっては訴訟リスクを軽減し、従業員にとっては退職金を確保できるという、双方にメリットがある解決策となる可能性があります。
|
💡 無料資料ダウンロード: しっかりマスター労働基準法~解雇編~(東京労働局) トラブルになりやすい「解雇のルールと手続き」をわかりやすく解説しています。
|
懲戒解雇との違いと退職金への影響
諭旨解雇と懲戒解雇の最も大きな違いは、退職金の取り扱いにあります。当事務所で対応した沖縄県内の製造業(従業員30名規模)の事例では、度重なる無断欠勤と業務命令違反があった従業員に対し、諭旨解雇を選択することで、退職金の一部支給と引き換えに円満な退職を実現しました。
統計データによると、諭旨解雇の場合は55.2%の企業が何らかの退職金を支給しているのに対し、懲戒解雇では63.2%が全額不支給としています(出典:企業における懲戒制度の最新実態 一般財団法人労務行政研究所)。沖縄の中小企業では、従業員との関係性が密接であることが多く、完全な対立を避けるために諭旨解雇を選択するケースが見受けられます。
就業規則への記載が必要な項目
諭旨解雇を適法に実施するためには、就業規則に明確な規定が必要です。沖縄県内の企業では、就業規則の整備が不十分なケースが散見されますが、これは重大な法的リスクとなります。
就業規則には、懲戒処分の種類として「諭旨解雇」を明記し、適用される具体的な事由(例:横領、重大な服務規律違反、ハラスメント行為など)を列挙する必要があります。また、退職勧告に応じない場合は懲戒解雇に移行する旨も明記しておくことが重要です。
諭旨解雇を適切に行うための必須要件と手続きフロー
諭旨解雇は懲戒処分である以上、厳格な手続きが求められます。特に沖縄のような地域密着型の企業環境では、手続きの不備が地域での評判に影響することもあるため、より慎重な対応が必要です。
適切な諭旨解雇を実施するためには、まず問題行為の客観的な証拠収集が不可欠です。口頭での注意だけでなく、書面による指導記録、改善指導の経過、他の従業員の証言などを体系的に収集・保管することが求められます。
| 項目 | 諭旨解雇 | 懲戒解雇 | 普通解雇 |
|---|---|---|---|
| 退職金 | 一部または全額支給(規定による) | 原則不支給 | 全額支給 |
| 解雇予告 | 形式上不要(自己都合退職扱い) | 労基署の認定があれば不要 | 30日前予告または予告手当必要 |
| 失業給付 | 給付制限期間あり(2-3か月) | 給付制限期間あり(3か月) | すぐに受給可能 |
| 手続きの厳格性 | 弁明の機会付与が必須 | 弁明の機会付与が必須 | 解雇理由の説明で足りる |
弁明の機会付与と証拠収集の重要性
諭旨解雇において最も重要な手続きの一つが、従業員への弁明の機会(聴聞の機会)の付与です。これは単なる形式的な手続きではなく、処分の公平性を担保する必須要件です。
具体的には、処分を検討していることを本人に通知し、問題とされる行為について説明を求める面談を実施します。沖縄の企業文化では、直接的な対立を避ける傾向がありますが、この手続きを省略すると、後に不当解雇として処分が無効となるリスクが極めて高くなります。
面談では、第三者(例:総務責任者や労務担当者)を同席させ、やり取りを記録として残すことも重要です。従業員の弁明内容によっては、処分を軽減する判断材料となることもあります。
沖縄の中小企業が陥りやすいトラブルと予防策
沖縄県内の中小企業では、就業規則の未整備や、段階的な指導プロセスの不足により、諭旨解雇が不当解雇と判断されるケースが少なくありません。特に従業員数が50名未満の企業では、労務管理体制が不十分なことが多く、トラブルに発展しやすい傾向があります。
不当解雇と判断されやすい3つのケース
第一に、軽微な違反に対していきなり諭旨解雇を適用するケースです。例えば、遅刻が続いたという理由だけで諭旨解雇を実施すると、処分の相当性を欠くとして無効となる可能性が高いです。段階的な指導(口頭注意→書面注意→減給処分など)を経ることが原則です。
第二に、就業規則に諭旨解雇の規定がないまま実施するケースです。沖縄の中小企業では「うちなータイム」的な緩やかな職場文化もあり、規則の整備が後回しになりがちですが、これは致命的なリスクとなります。
第三に、誓約書の提出を強要し、拒否を理由に解雇するケースです。「今後一切異議を申し立てません」といった包括的な権利放棄を求める誓約書は、従業員の正当な権利を侵害するものとして無効と判断されます。
専門家への相談タイミング
諭旨解雇を検討する際は、実施前の早い段階で社会保険労務士などの専門家に相談することが不可欠です。特に以下のタイミングでは、必ず専門家の助言を得るべきです。
まず、問題行動が発覚した初期段階での相談が重要です。証拠収集の方法や、段階的指導の進め方について、法的観点からのアドバイスを受けることで、後のトラブルを予防できます。次に、懲戒処分を検討する段階では、処分の相当性や手続きの適正性について専門的な検証が必要です。最後に、退職勧告を行う前には、勧告文書の内容や面談の進め方について具体的な指導を受けることが推奨されます。
まとめ
諭旨解雇は、懲戒解雇よりも穏便に雇用関係を終了させる手段として有効ですが、適切な手続きを踏まなければ不当解雇のリスクを抱えることになります。沖縄の中小企業においては、就業規則の整備、段階的な指導の実施、弁明の機会の付与という3つの要件を確実に満たすことが、トラブル回避の鍵となります。
今日から始められる3つのステップ:
- 現在の就業規則に諭旨解雇の規定があるか確認する
- 問題行動に対する指導記録を書面で残す体制を整える
- 労務管理の専門家に現状の課題についてアドバイスを求める
|
📞 無料相談のご予約 労務管理でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。 初回相談は無料です。 |
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由




