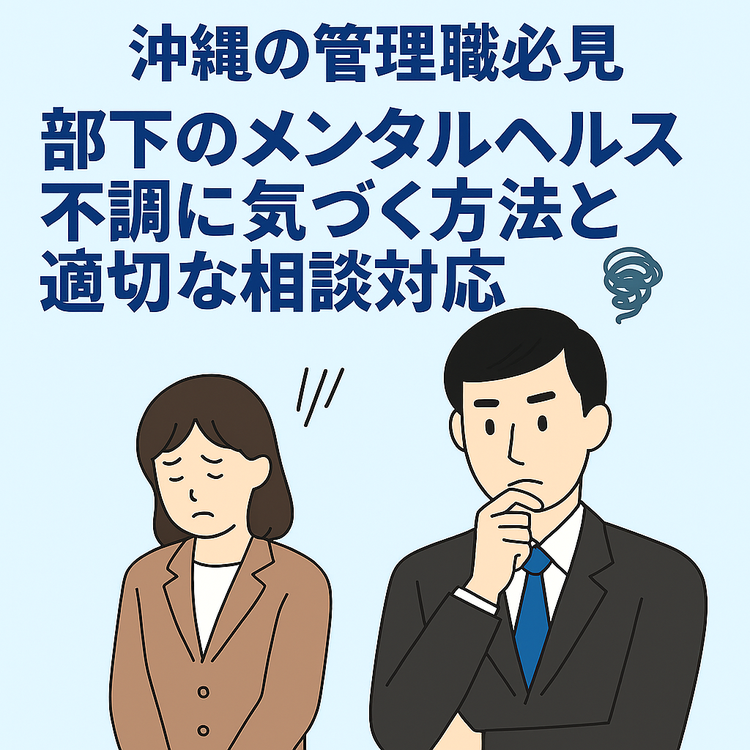
「最近、部下の様子がいつもと違う気がする…」「メンタルヘルスの相談を受けたけれど、どう対応すればいいのか分からない」――こんなお悩みを抱えていませんか?
沖縄の中小企業では、観光業の繁閑期や独特の職場文化の中で、従業員のメンタルヘルス対策が重要な経営課題となっています。本記事では、社会保険労務士・キャリアコンサルタントの視点から、管理職が知っておくべき部下のメンタルヘルス不調の気づき方と、適切な相談対応の方法を具体的に解説します。読了後には、明日から実践できる予防的アプローチが身につきます。
部下のメンタルヘルス不調に気づくための観察ポイント
メンタルヘルス対策の第一歩は、部下の変化に早期に気づくことです。重要なのは「本人の通常の行動様式からのズレ」に着目することです。
「いつもと違う」サインを見逃さない5つのチェック項目
厚生労働省「こころの耳」が示す初期サインには、以下のような具体例があります。
- 勤怠の変化: 以前と比べて遅刻や欠勤が増えた、休憩時間に一人で過ごすようになった
- 身体的サイン: 顔色が悪い、疲れた表情が続いている、身だしなみが乱れてきた
- 業務パフォーマンス: 仕事の能率が低下している、ミスが目立つようになった
- コミュニケーションの変化: 口数が少なくなった、同僚との交流を避けるようになった
- 生活習慣の乱れ: 飲酒量や喫煙量が増えた、食欲がないと話すようになった
このような徴候に気づいたら、まずは個別に時間を取って話を聴くことが大切です。アドバイスよりも、その人の気持ちを十分に受け止める姿勢が重要となります。
沖縄の企業でよく見られる職場ストレスの特徴
沖縄県内の中小企業では、観光業における繁閑期の労働時間の変動、少人数体制による業務負荷の集中、人間関係の密接さゆえの人間関係トラブルなど、地域特有のストレス要因が存在します。当事務所でも、こうした環境下でのメンタルヘルス相談に数多く対応してきました。
| 観察項目 | 具体的なサイン例 | 初期対応のポイント |
|---|---|---|
| 勤怠の変化 | 遅刻・欠勤の増加、休憩時間の過ごし方の変化(一人で過ごすようになった) | 個別に声をかけ、体調や最近の様子を気遣う。プライバシーに配慮した個室での面談を検討 |
| 業務パフォーマンス | ミスの増加、仕事の能率低下、判断力の低下、報告・連絡・相談の減少 | 業務負荷の見直しを行い、必要に応じて産業医面談や保健師への相談を提案する |
| 身体的サイン | 顔色が悪い、疲れた表情が続く、身だしなみの乱れ、体調不良の訴え | 十分な休息を促し、継続する場合は医療機関の受診を勧める。産業保健スタッフとも情報共有 |
| コミュニケーションの変化 | 口数が減る、同僚との交流を避ける、表情が乏しくなる、昼食を一緒に取らなくなった | 押し付けがましくならない範囲で声をかけ、話を聴く機会をつくる。孤立させない配慮 |
| 生活習慣の乱れ | 飲酒・喫煙量の増加、食欲不振、睡眠障害(眠れない、途中で目が覚める) | 率直に心配している気持ちを伝え、社内の産業保健スタッフや外部相談機関への相談を促す |
相談を受けたときの適切な対応と避けるべき言動
部下や同僚から心の不調について相談されたとき、どのように対応すればよいでしょうか。
傾聴の基本姿勢とプライバシー保護の重要性
相談対応の基本は、時間をつくって話を聴くこと、相談内容を正確に把握し、必要な支援につなげることです。
対応時の重要ポイント:
- 個室で対応する: 他の人に話が聞こえない環境を確保します。お酒の席での相談対応は避けましょう。
- 傾聴に徹する: すぐにアドバイスや励ましをしたくなりますが、心の不調の場合は逆効果になることがあります。まずは相手の気持ちを受け止めることを優先します。
- 専門家につなぐ: 眠れない、食欲がない、疲れやすいなどの体調不良や、飲酒・喫煙量の増加に気づいたら、産業医や保健師、社外の相談機関への相談を促します。
プライバシー保護の徹底: 本人から聴いた個人情報を不必要に他者へ伝えてはいけません。他の人へ伝える必要がある場合も、原則として本人の了解を得た上で、必要最低限の範囲に留めます。病名を伝える必要はなく、「残業制限が必要」「軽作業への配置転換」など、具体的な配慮内容に焦点を当てます。
パワハラとメンタルヘルスの密接な関係
パワー・ハラスメント(職場において、職権などの力関係を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言動)は、被害を受けた従業員のメンタルヘルス不調に直結します。
当事務所で対応した沖縄中部地域のサービス業の事例では、繁忙期の長時間労働に加えて上司からの厳しい叱責が重なり、部下が心身の不調を訴えたケースがありました。管理職の方が早期に気づき、産業医面談の設定と業務負荷の見直しを実施したことで、休職せずに職場復帰を支援できました。
部下や同僚のハラスメント被害に気づいたら、プライバシーに十分配慮しつつ真摯に話を聴き、「本人にも問題がある」といった発言は避けます。メンタルヘルス不調の徴候があれば、産業保健スタッフへの相談を勧めます。
|
📄 事例資料ダウンロード: 働く人のメンタルヘルスガイド職場のメンタルヘルス対策実践ガイド 東京都労働相談情報センター
働く人の心の健康(メンタルヘルス)を確保し、誰もがいきいきと働ける職場づくりを実現するために、メンタルヘルスやラインケア・セルフケアの概要とご利用いただける制度や資料が紹介されています。
|
職場でできる予防的サポートと専門家への橋渡し
相談対応と並行して、職場全体でメンタルヘルス不調を予防する体制づくりが重要です。
過重労働の回避と柔軟な働き方の調整
長時間の残業や深夜業務など過重な負荷が続くと、睡眠時間の減少により脳・心臓疾患やうつ病のリスクが高まります。労働安全衛生法では、長時間労働者への医師による面接指導が義務付けられています。
職場でできる具体的なサポート:
- 短時間勤務、軽作業や定型業務への配置
- 残業・深夜勤務の免除
- フレックスタイム制度の活用
- 定期的な面談による業務負荷の確認
沖縄県では、雇用関連の助成金制度も活用できます。職場環境の改善や従業員支援に関する相談は、社会保険労務士などの専門家にお気軽にお問い合わせください。
専門家・相談機関の活用: 社内の産業医、産業保健スタッフ、社外では沖縄県精神保健福祉センター、労災病院の「心の電話相談」、全国の保健所の「こころの健康相談」などが利用できます。民間では「いのちの電話」や日本産業カウンセラー協会の「働く人の悩みホットライン」など無料相談窓口もあります。
まとめ: 明日から始める予防的メンタルヘルス対策
部下のメンタルヘルス対策は、企業の持続的成長と従業員のウェルビーイング(心身の健康と幸福)を両立させるための重要な経営課題です。
今日から始められる3つのステップ:
- 日常的な観察: 部下の「いつもと違う」サインに気づくための観察項目を確認する
- 相談しやすい環境: プライバシーに配慮し、傾聴の姿勢で話を聴く場をつくる
- 専門家との連携: 早期に産業保健スタッフや外部相談機関につなぐ体制を整える
メンタルヘルス対策は、トラブルが起きてから対応するのではなく、予防的なアプローチが最も効果的です。沖縄の企業文化に適した対策を、一緒に考えていきましょう。
|
📞 無料相談のご予約 労務管理やメンタルヘルス対策でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。 初回相談は無料です。
|
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由




